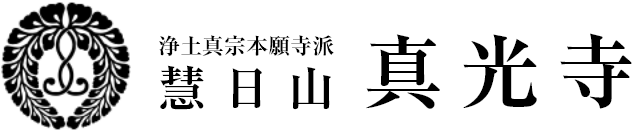娑婆の縁つきるとき

「私は何のために生まれてきたのか」「この苦しみはいつまでつづくのか」「死んだらどこに行くのか」・・・誰しも人生について、いろいろな問いを持っているのではないかと思います。
しかしその問いが根源的であればあるほど、おいそれとは口に出しづらいのではないでしょうか?
今回は、「死に際してどんな心構えをすれば良いのか」という問いについて考えてみたいと思います。
☆PDFはこちら⇒No.190

「おひとりさま」を生き抜く
日本のフェミニズム運動を引っ張ってきた方で、東京大学名誉教授を務める上野千鶴子さん。10年ほど前に『おひとりさまの老後』という本を書き、ベストセラーとなりました。
家族のいない者にとっての、死との向き合い方や介護を受けるにあたっての心構え十カ条など、軽やかな筆致で「ひとり」を生きる知恵をつづられています。
『おひとりさまの老後』
上野千鶴子 著(文春文庫)より
歳をとるとは、自分の弱さを認めるということだ。
毅然としていたり、凛としていたり、気骨のあるお年寄りというのはたしかにいらっしゃるが、そのまねが自分にできるとは思えない。病気で苦しめば痛みにぴいぴい泣きそうだし、死期を宣告されれば取り乱しそうだ。
わたしの父は医者で、自分が治療の手だてのない末期がんの患者であることを知っていたが、死の床で動揺をくりかえし、ちっとも死の準備なんかできていなかった。
それがふつうの人間だろう。
父の介護に際して、友人、知人の介護経験をさんざん聞いたが、りっぱな人間のりっぱな死に方は、いくら聞いてもなんの参考にもならなかった。「そんな人もいるでしょうね」という感じだ。万人がそのような毅然とした死を迎えるわけではない。…
人間は弱い。動揺する。昨日考えたことを、今日になって翻すこともある。

誰にでも初めての経験である「死」
実際、死に臨んで平静でいられる人の方が少ないと思います。
「仏教の教えを聞いていたから」とか「人の死にたくさん立ち会ってきたから」ということは、あまり役に立たないと考えた方が良さそうです。
なにせ自分自身の死は、初めての体験だからです。私も、まったく自信がありません。
私たちの宗祖・親鸞聖人のことばに、次のようなものがあります。
苦しく悩みの尽きないこの世(娑婆)であるのに、なかなか捨てがたいものです。いくら苦悩から解放されると言われても、安楽の浄土を恋しく思うことができません。
それは、自分自身の煩悩がなせる業です。
私たちは、名残惜しく思いながらも娑婆の縁つきて、力なく命終えていかねばならなくなってから、お浄土に参らせていただきましょう。
『歎異抄 第九条』より住職意訳

人間の弱さにこそ寄り添う
親鸞聖人も、「自分は煩悩のせいで生にしがみつこうとするだろう」とおっしゃいます。そしてそうした人間の弱さに寄り添ってくれるのが、阿弥陀如来だと喜ばれました。
急いでお浄土参りをしたがらない者をこそ、ことに憐れんでくださるのが阿弥陀さまです。
これにつけても、いよいよ阿弥陀さまの大悲の願いは頼もしく、私がお浄土へ往生し、覚りを得て仏と成ることは間違いないと思えるのです。
私たちも最後まで生にしがみつきながら、お念仏と共に娑婆の命をまっとうし、ゆっくりとお浄土に参らせていただきましょう。
出典
上野千鶴子『おひとりさまの老後』(文春文庫)をクリック
解説;もうちょっと知りたい(お経のこと)
~参照先~
問答によって生まれるもの
仏教の経典は、その多くがお釈迦さまと弟子たちの問答によって成り立っているといえます。
『大無量寿経』では、阿難尊者が「なぜ今日は、お釈迦さまのお顔が特別に光り輝いておられるのですか?」という問いを発したところから阿弥陀如来の四十八願(本願)が説かれ始めました。
<『浄土真宗聖典』p8>
参照「他力本願」⇒👉No.176の解説を見る
また『観無量寿経』では、韋提希夫人が「私はどうしてこのような子(親を殺そうとするような子)を産むことになったのでしょうか?」という嘆きをぶつけたところから、お釈迦さまは定善十三観・散善三観を説き始め、阿難尊者が「お釈迦さまのお説きになられた教えの要をどのようにたもてば良いのですか?」と問うたのに対して「無量寿仏(南無阿弥陀仏)の名をたもて」とおっしゃり、念仏を勧められたのでした。
<『浄土真宗聖典』p90/p117>
参照「南無阿弥陀仏」⇒👉No.164の解説を見る
今回ご紹介した親鸞聖人のことばも、唯円という弟子との問答の一部です。唯円は親鸞聖人よりもおよそ50歳年下。80代の聖人のことばを30代の唯円が聞き、それを後に書き記したのが『歎異抄』です。
少し長いですが、その問答を見てみましょう。
<『浄土真宗聖典』p836>
「念仏しておりましても、踊りあがるような喜びの心がそれほど湧いてきませんし、また浄土に往生したいという心が少しも起こってこないのは、どのように考えたらよいのでしょうか」とお尋ねしたところ、次のように仰せになりました。
この親鸞もなぜだろうかと思っていたのですが、唯円房よ、あなたも同じ心持ちだったのですね。
よくよく考えてみますと、踊りあがるほど大喜びするはずのこと(浄土に往生し仏の覚りを得ること)が喜べないから、ますます往生は間違いないと思うのです。喜ぶはずの心が抑えられて喜べないのは、煩悩のしわざなのです。
そうしたわたしどもであることを阿弥陀仏ははじめから知っておられて、「あなたはあらゆる煩悩を身にそなえた凡夫だ」と仰せになっているのです。ですから阿弥陀仏の本願は、凡夫であるわたしどものために大いなる慈悲の心をおこされたのだと気づかされ、ますます頼もしく思われるのです。
また、浄土にはやく往生したいという心がおこらず、少しでも病気にかかると「死ぬのではないだろうか」と心細く思われるのも煩悩のしわざです。
果てしなく遠い昔からこれまで生まれ変わり死に変わりし続けてきた、苦悩に満ちたこの迷いの世界なのに捨てがたく、まだ生まれたことのない安らかなさとりの世界(浄土)なのに心ひかれないのは、まことに煩悩が盛んだからなのです。どれほど名残惜しいと思っても、この世の縁が尽き、どうすることもできないで命終えるとき、浄土に往生させていただくのです。
はやく往生したいという心のないわたしどものようなものを、阿弥陀仏はことのほかあわれに思ってくださるのです。
このようなわけであるからこそ、大いなる慈悲の心でおこされた本願はますます頼もしく、往生は間違いないと思います。踊りあがるような喜びの心が湧きおこり、また少しでもはやく浄土に往生したいというのでしたら、「わたしには煩悩がないのだろうか」と、かえって疑わしく思われることでしょう。
このように聖人は仰せになりました。
『歎異抄 第九条』より
参照「浄土」⇒👉No.021の解説を見る
「凡夫」という私自身のあり方と、それを救わんとする阿弥陀如来の大悲のはたらきを見事に表した問答です。
そして親鸞聖人の逆説的ともいえる独特の表現を引き出したのが、唯円による「喜びの心が湧いてこないのですが…」という、50歳年上の師匠に向けたおそるおそる(?)の問いかけでした。
阿弥陀如来の救いは「不可称・不可説・不可思議」と言われます。人間の知恵では「たたえ尽すことも、説き尽くすことも、思いはかることもできない」というのです。
逆に言えば、「わかった・理解できた」と思った瞬間、それは狭い自分の料簡に閉じ込めてしまうこととなり、本来の救いとはかけ離れたものとなってしまうのです。
(かくいう私も、阿弥陀如来やその救いについて「わかりやすく書こう」としている時点で、だいぶ矛盾を抱えているのですが…。本当は、「ただ味わう」ことしかできないのかもしれません。)
いずれにせよ、わかってもいないのにわかったような顔をせず、わからないことを素直に問うていった先達がいてくださったおかげで、私たちのもとに尊い教えが遺されていることを喜びたいと思います。
どうか、皆さんそれぞれの「問い」を大切にしていってください。
用語一覧を見る ⇒ ここをクリック