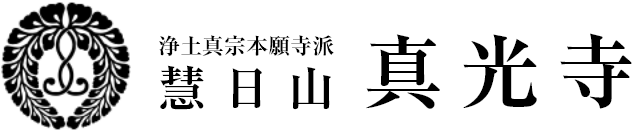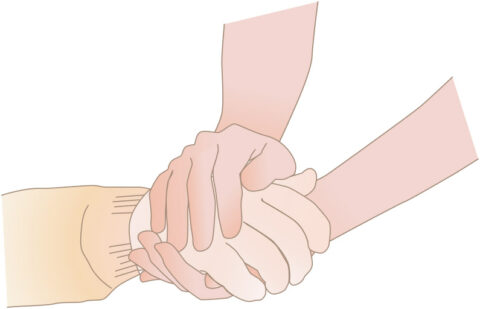いのちのふるさと

現代の日本人は、男性の二人に一人・女性の三人に一人が、何らかの癌(ガン)を患うというデータがあります。
「癌」という字を見るといまだにドキッとしますが、最近は初期の段階で見つけることもできるようになり、“不治の病”から“長く付き合っていく病”に変わってきました。
また、お医者さんの中には「自分は癌で死にたい」という方も多いそうです。その理由は、「大切な人とのお別れがゆっくりできるから」です。

では大切な人とのお別れの時、あなたならどんなことを語り合いますか?
患者を励ますつもりで、つい「また元気になったら…」と前向きな話をしたくなります。
それも良いかもしれませんが、実は患者本人はもう治らないことを感じ取り、ただこちらに話を合わせてくれているだけかもしれません。むしろ患者側に気をつかわせてしまっていることもあるのではないでしょうか?
看取りの時、どんなことを語り合うのか…。それを考えさせてくれる「ことば」をご紹介します。
☆PDFはこちら⇒ No.021
田代俊孝 著
『心を支える・ビハーラ』(法蔵館) より
お浄土に帰るんだから大丈夫だよ。阿弥陀さまが守っていてくださるんだから…。南無阿弥陀仏を唱えていけば大丈夫だよ。
あんなに会いたがっていた母さんに会えるんじゃない。可愛がってくれたおばあちゃんにも。父さん母さんは、火を灯して待っていてくれるよ。
姉さんも、きっと行くから待っていてね。
「いのちのふるさと」を持っていますか?
これは、宮崎正子さんという看護師の女性が、最愛の妹・三知子さんを40代の若さで見送った時、ベッドでかけ続けた言葉です。
それまで宮崎さんが看護師として看てきた患者さんの中には、告知をされず、「わたし、ガンなんじゃないの?」と周囲を疑うことで次第にまわりの人も見舞いに行きにくくなり、ついには家族とさえ信頼関係を失ったまま死を迎える人が数多くいたといいます。
幼い頃に母親を亡くし、二人で寄り添うように生きてきた妹の三知子さん。
その妹が病に伏した時、宮崎さんは、手探りながらもできる限り、やがて行く「いのちのふるさと」について語り合いました。
死は人生の一部
宮崎さんをサポートしてきた「死そして生を考える研究会」代表の田代俊孝さんは、告知のあり方は家族それぞれの事情によると前置きした上で、次のように語っています。
今なぜ私たちが苦しみを持ったり、悲しみを持ったりするのかといえば、やはり死をタブーにしているからなんですね。
生はプラス、死はマイナス。
ところが現実には、私たちはみな「死すべき身」なんですね。
だから、死ということをきちっと人生の一つであると見すえていくという、そいういった学びが普段から我々には必要なんじゃないかと思います。
この妹さんは、死ということに直面して、思いを超えた命を支える世界、大きな世界があるんだという、そういう出逢いがあったんだと思います。

看取りは「我がこと」
大切な誰かを失った時、あるいは失おうとしている時、死についてはできるだけ触れないでおくのか、それとも「命を支える世界・大きな世界」を思いながら・語りながら見送るのか。
たいへん難しい問題ですが、いま一度考えてみるのが、残された者の務めなのではないかと思います。
再び大切な誰かを看取る時のために。そして、自らが看取られる時のために…。
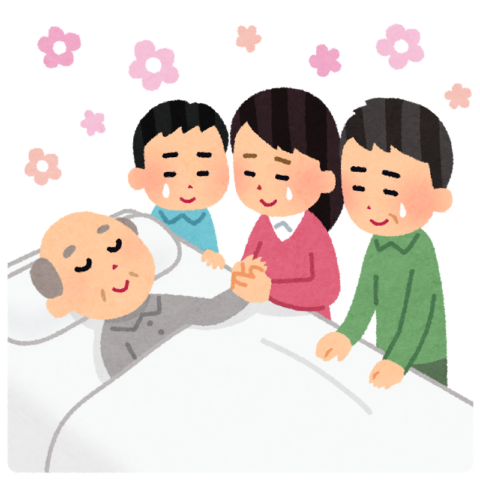
あとがき;日頃からの お聞かせ
「死んだ先のことなど、今はまだ考えたくない」と思われる方がいるかもしれません。
しかし、いざ身近な方を看取る状況になった時・自分が看取られる状況になった時、「命の帰る先はどこか?」とあわてて考えても、短い時間では納得できる答えは得られないでしょう。
だからこそ、元気な時(お寺に参れる時・聴聞できる時・仏教を学べる時)に、「命の帰る先はどこか?」を聞かせていただくことが大切です。
科学中心の社会に育ってきた私たちは、「実証できるもの(目に見えるもの)以外は信じない」という癖がついています。最初は「浄土」などと聞いても、うなずくことができないかもしれません。
しかし「煩悩から逃れられない私の命を、どこが引き受けてくれるのか」をよくよく考えてみれば、きっと阿弥陀如来の浄土以外にはないことを知ることになるでしょう。
どうか、日頃からのお聞かせに耳を傾けてみてください。
煩悩 … 参照「他力本願」⇒👉No.176の解説を見る
最期の時までに何らかの形で、「今までありがとう。私も後から行くからね」と、あるいは「先に行って待っているからね」と大切な人に伝えたい。
私自身もそう思っています。
原本を読みたい方は、
田代俊孝『心を支える・ビハーラ』~講座「いのちの教育」1~(法蔵館)
をクリック。
解説;もうちょっと知りたい(お経のこと)
~参照先~
「浄土」とは何か
浄土真宗では、「命の帰る先・いのちのふるさと」のことを「極楽浄土」と呼びます。阿弥陀如来に抱かれて、私たちが必ず救われていく(煩悩から解放されていく)覚りの世界のことです。
親鸞聖人は『教行信証』信巻のなかで、次のように述べています。
<『浄土真宗聖典』p264>
念仏をいただいた者は、如来からまちがいない信心をいただいているから、この世の命を終えて浄土に生まれ、たちまちに完全なさとりを開く。
「極楽というからには、楽しいことばかりが待っているだろう。」と思われがちですが、本来は、阿弥陀如来と同じ覚りをいただけるのが極楽浄土です。
阿弥陀如来の覚りとは、完全なる智慧を得て、自らの煩悩から解放されることを指します。そしてそれだけでなく、悲しみや苦しみを抱える他者を救いとげようと、完全なる慈悲のはたらきをすることも意味します。
阿弥陀如来のはたらきについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
『仏説無量寿経』では、阿弥陀如来のはたらきを十二の光にたとえています。
<『浄土真宗聖典』p29>
少し長いですが、中国の高僧・曇鸞大師の解釈(『讃阿弥陀仏偈』)も加えて記します。
無量光(智慧の光ははかり知ることができず、迷いの世界の者はみな、その光に照らされる)
無辺光(さとりの光は限りがなく、その光に照らされた者はすべてのとらわれを離れる)
無礙光(光は虚空のように何ものにもさまたげられず、迷いの世界の者はすべてその光のはたらきを受ける)
無対光(清らかな光は並ぶものがなく、この光に遇えば、迷いの世界につなぎとめる行いも力が失われる)
炎王光(仏の光は耀きがもっともすぐれており、苦しみの世界の闇もその光によって除かれる)
清浄光(さとりの智慧の光は明るく輝き、すべてのものに超えすぐれている。その光にひとたび照らされると、罪が除かれみなさとりを得ることができる)
歓喜光(慈悲の光は広くすべての者を照らして安らぎを与える。その光が届いた人々は、仏の恵みに喜びの心をおこす)
智慧光(仏の光は無明の闇をすべて破る。すべての仏・菩薩・声聞・縁覚にいたるまで、ことごとくこの仏をたたえる)
不断光(その光はいつも絶えることなくすべてを照らす。その光のはたらき、すなわち仏の本願を聞き信じる者は、その信が一生を通して絶えることはなく、みな往生することができる)
難思光(その光は仏でなければはかり知ることができない。すべての仏は阿弥陀仏による衆生の往生をほめ、この仏の功徳をたたえる)
無称光(その不可思議な光は姿かたちを超えていて、どのような言葉でも説き示すことができない)
超日月光(仏の光の耀きは日や月の光に超えすぐれている)
こうした阿弥陀如来の光は、煩悩という暗闇のなかにいる私たちにも届き、どんな時でも照らし続けています。そのはたらきにおまかせするからこそ、私たちは浄土に往生し、さとりをいただくことができるのです。
親鸞聖人が浄土について記した『教行信証』真仏土巻には、次のような文章があります。
<『浄土真宗聖典』p337>
浄土とは、無量光明土である
浄土のありさまにも使われている「光」。この短い一文は、たいへん重要なことを示しています。
すなわち、浄土は阿弥陀如来によって建立された完全な覚りの世界であり、そこに往生するということは、阿弥陀如来と同じ完全な覚りを得るということです。
そして、浄土に往生した者は、阿弥陀如来と同じ無量光・無辺光・無礙光…のはたらきをするということも示しています。
先に亡くなった私たちの父や母、つれあいや兄弟、友やわが子でさえ、この私を支え導く「光」となり、はたらいてくださるというのです。
さらに、私たち自身が「いのちのふるさと」に帰っていくことで、今度は私たちがこの世に残した大切な人のためにはたらく「光」になっていくことに他ならないのです。
これを「還相回向(げんそうえこう)」といいますが、またいずれ別の形で書きたいと思います。
親鸞聖人は、『教行信証』真仏土巻のなかで、中国の高僧・善導大師による次のようなことばを引いています。
<『浄土真宗聖典』p369>
西方(極楽)浄土は煩悩を滅しつくした、変わることのない覚りの世界である。すべてのとらわれを離れ、はからいがない。
西方浄土に生まれると、大いなる慈悲の心を起こしてあらゆる世界に行き、さまざまな姿を現して人々を等しく救済する。
さあ帰ろう、迷いの世界にとどまるべきではない。
はかり知れない昔から、さまざまな迷いの世界に生まれ変わり死に変わりし続けてきた。どこにも何の楽しみもなく、ただ嘆き悲しみの声ばかりである。
この一生を終えた後には、覚りの浄土へ往こう。
「いのちのふるさと」に帰ることは悲しく寂しいだけではないことを、大切な人との別れだからこそ、共有しておきたいと思います。
用語一覧を見る ⇒ ここをクリック